はじめに
きゅうがめら‼︎ぺいです‼︎
※ 15分程度で読めます。
最近、左の胸の痛みや左の顎関節部の痛みがあり、体調はそれほどいいとは言えません。
もうすぐ40歳だし、歳かなーなんてのも感じていますが、健康じゃなきゃこの先の人生も楽しめない。今年からまずは健康を意識して色々試してはいるのですが、果たして効いているのか・・・
でも続けなければ意味ないので続けていますが、自分に合っていないとこれまた意味ない。
ただ、1番いいと実感しているのは早起きですね。
とまあ、健康に関しては今度書くとして今回はタイトル通り医療費系について。
日本の公的保険は世界一と言われるほどかなり整っています。
民間保険は、家族がいるなら生命保険(掛け捨て)、自動車保険、火災保険だけでいいと思ってます。
んまーこれもなんでってのは今後書いていきますね。
では、はじめていきますー。
医療費とは??
医療費の基本
日本では、病院でかかった医療費の全額を自分で払うわけではありません。健康保険に入っていれば、原則として医療費の3割(小学生未満や高齢者は2割または1割)だけを自己負担します。
でも、大きな病気や手術などで1か月の医療費が高額になると、3割でもかなりの負担になりますよね。
そこで登場するのが「高額療養費制度」です。
高額療養費制度とは?
1か月(1日〜月末まで)の医療費の自己負担額が、ある上限額を超えた場合、その超えた分はあとで払い戻される制度です。
この上限額は、年齢や所得に応じて異なるため、収入が少ない人ほど負担が軽くなる仕組みになっています。
例えばですが・・・
高額療養制度の自己負担限度額の目安(69歳以下の場合)
(70歳以上は別の基準がありますが、ここでは69歳以下を中心に説明します)
| 所得区分 | 区分の目安 | 自己負担限度額(月) |
| 年収約1,160万円~ | 上位所得者 | 約252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 年収約770~1,160万円 | 高所得者 | 約167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 年収約370~770万円 | 中間層 | 約80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 年収約~370万円 | 住民税非課税世帯以外 | 約57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 低所得者 | 約35,400円 など |
では具体例でシミュレーションしてみましょう!
● ケース1:年収500万円のAさんが、1か月に100万円の医療費がかかった場合
Aさんの自己負担割合は3割 →
100万円 × 30% = 30万円 が本来の自己負担額。
でもAさんの限度額は【約87,430円】(80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%)なので…
→ 30万円 − 87,430円 = 約21万2,570円が後日戻ってくる!ということになります。
注意点:事前に「限度額適用認定証」をもらおう
高額療養費は基本的に一度払ってから払い戻される制度ですが、「限度額適用認定証」をあらかじめ健康保険組合などに申請しておけば、窓口での支払いが最初から上限額までで済みます。ただし、マイナンバーカードでしたら自動的に適用される点も覚えておきましょう。
手術や入院が予定されているなら、ぜひ事前申請をおすすめします。
高額療養費制度まとめ
• 医療費が高額になっても、高額療養費制度で負担を抑えられる
• 月単位(1日〜月末)での計算
• 年収によって上限が変わる
• 事前に「限度額適用認定証」があれば安心!
医療費控除とは?
1年間(1月1日〜12月31日)に、自分や家族のために一定額以上の医療費を支払った場合に、確定申告をすると税金が安くなる制度です。
これは、医療費がかさんで家計が苦しいときに、その負担を少しでも軽くするための仕組みです。
医療費控除の対象となる金額の計算方法
次のように計算します:
医療費控除額 = 実際に払った医療費の合計 - 保険金などで補填された金額 - 10万円(または所得の5%)
※「10万円」は年収が200万円未満の人は「所得の5%」に変わります。
医療費控除の上限
最大で200万円まで控除が認められます。
医療費控除の対象になるもの
実は病院代だけではありません。以下のようなものも含まれます:
| 対象になるもの | 対象外のもの |
| 通院のための交通費(バス・電車) | マイカーのガソリン代、駐車場代 |
| 医師の処方による薬代 | 健康食品、サプリ |
| 歯科治療(保険・自費もOK) | 美容目的の矯正やホワイトニング |
| 入院費・手術代 | 入院時のパジャマ代やテレビ代 |
| 妊娠・出産の費用(一定条件) | 美容整形、予防接種 |
具体例で説明してみましょう!
● ケース2:1年間で医療費が60万円かかったBさん(年収400万円)
• 実際に払った医療費:60万円
• 保険などで戻ってきたお金(高額療養費や民間保険など):20万円
• 所得が200万円以上なので、差し引くのは10万円
控除額の計算:
60万円 − 20万円 − 10万円 = 30万円 → この30万円が所得控除になる
→ 結果として、払うべき税金が減って戻ってくる可能性あり!
⸻
■ 手続き方法は?
• 確定申告(2月16日〜3月15日ごろ)に、医療費の領収書や明細書を添えて提出
• e-Tax(インターネット)でも申告できます
• 会社員でも申告すればOK!(年末調整だけでは反映されません)
⸻
■ 高額療養費との違いと併用
→ 結果として、払うべき税金が減って戻ってくる可能性あり!
⸻
■ 手続き方法は?
• 確定申告(2月16日〜3月15日ごろ)に、医療費の領収書や明細書を添えて提出
• e-Tax(インターネット)でも申告できます
• 会社員でも申告すればOK!(年末調整だけでは反映されません)
高額療養費との違いと併用
| 比較項目 | 高額療養費制度 | 医療費控除 |
| 内容 | 医療費の自己負担額に上限を設ける | 税金を安くする(所得控除) |
| 手続き先 | 健康保険組合 | 税務署(確定申告) |
| いつの費用が対象? | 1か月単位 | 1年単位(1~12月) |
| 併用できる? | → 併用可能! 高額療養費で戻った分を差し引いて計算 |
医療費控除のまとめ
• 医療費控除は、1年で10万円以上の医療費を支払った人が、税金を軽くできる制度
• 病院代だけでなく、通院交通費や歯医者、自費診療も対象になることがある
• 確定申告が必要なので、領収書は保管しておこう!
最後に
最初にも書きましたが、日本の公的保険は世界最強と謳われています。
でも、こういった内容は学校ではもちろん社会に出てからも誰もほとんど教えてくれません。
自分で勉強して身につけるしかないのです。
ぜひこの機会にマネーリテラシーを高めていきましょう。
間違いやご指摘がありましたらコメントしてくださると幸いです。
ここまで
読んでくれて
おぼらだれん٩( ‘ω’ )و
心song♪

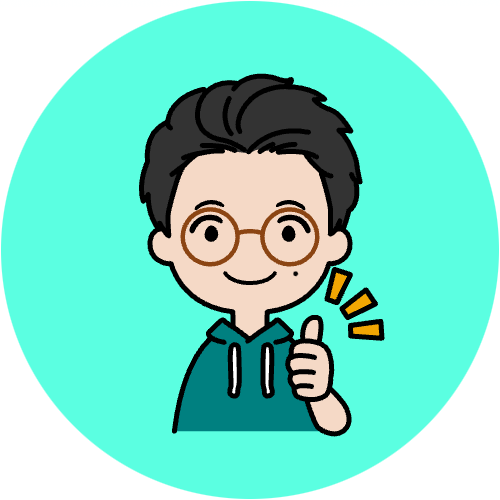

コメント